Rh式血液型は複雑で、血液型物質はまだ18種類しか確認されていない。
コロナ制圧タスクフォースによると
重症化リスクが最も低かったのはO型で
そのO型よりも
A型とB型は、およそ1.2倍
AB型はおよそ1.6倍
重症化リスクが高い
Dock2と呼ばれる遺伝子の近くにある化学物質が
"G"の人に比べて"A"の人は2倍
重症になりやすかった
https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2021/5/18/210518-1.pdf
免疫力の高い血液順
O > B > A > AB
A型は抗B抗体をもつ
B型は抗A抗体をもつ
AB型は、どちらももたない
O型は、どちらももっている
抗A抗体は、新型コロナと受容体ACE2が結合することを邪魔する。
O型は、血栓症を起こしにくい。
O型は、血液凝固因子フォン・ヴィレブランドが少ない。
逆に言えば、止血しにくい。
O型は、胃酸の分泌量が多いため、何でも食べられる。
狩猟民族から農耕民族になるにつれて、肉から穀物や野菜を消化しやすい体になる過程で、O型からA型になっていた。
一方、狩猟民族から遊牧民族になる過程で、腸内細菌は動物性たんぱく質を好むウェルシュ菌から乳製品などの発酵食品を好む乳酸菌が主体になっていて、B型になっていった。
そして、A型とB型が交雑することでAB型が生まれた。
ABO式の血液型物質は糖鎖でできていて、糖の合成を可能にしたのが原始生物で、血液型物質を最初に合成したのは細菌で、人類は腸内細菌から血液型物質を受け取っていった。実際に、胃や腸で分泌される粘液の中には、血液中よりも血液型物質が多い。
O型はリンパ球人間→副交感神経が優位
AB型は顆粒球人間→交感神経が優位
A型は抗B抗体を血清中に持っているため、B型物質を持っている食べ物はあわない。
逆も真。
A型物質を認識するレクチン(糖鎖を認識するたんぱく質)を含む食品をA型の人が食べると、そのレクチンが赤血球や腸や胃などのA型物質と結合して、凝固反応し、炎症を起こす。
デザイナーズフーズピラミッド
その生活習慣対策に効果のある野菜をピラミッド型にまとめたもの。 ピラミッドの上位にあるほど健康効果が高い

目次
はじめに
第1章 なぜ、O型は新型コロナに感染しても重症化しづらいのか
免疫力ナンバーワンはO型、ツーはB型
血液型で免疫力は宿命的に違ってくる
細菌も血液型物質をもっている
血液型によって感染しやすい細菌は違う
O型とはもともと0(ゼロ)型だった
血液型物質の基本は、O型
なぜO型には、抗A抗体も抗B抗体もあるのか
O型は新型コロナの重症化率が低い
O型が重症化しにくいのは、遺伝子の違い
O型は集中治療室の滞在日数も短い
抗A抗体が新型コロナの動きを邪魔している?
新型コロナの重症化の一因は血栓症
発熱は病気を治そうとする免疫の反応
O型は血栓ができにくい体質をしている
O型は血液が固まりにくい
新型コロナワクチンの副反応に血栓症
コロナ重症化を防ぐメカニズム
第2章 血液型はどのように生まれたのか
血液型は、自分の免疫力を上げるトリセツ
ABO式の血液型は腸内細菌がつくり出した
微生物との過酷な闘いが血液型をつくった
血液型物質を最初にもったのは、細菌
人類はO型から始まった。
A型は農耕民族から生まれた
B型の祖先は遊牧民
AB型の人は10世紀ごろに初めて現れた
血液型の人口比は国によって異なる
コロンブスがヨーロッパをO型優位に変えた?
病気への抵抗力が性格を方向づける
A型の多い日本が梅毒で壊滅しなかったわけ
A型は几帳面だからこそ、農耕生活に適応できた
O型を好んで襲いかかる感染症もある
天然痘にはA型とAB型が弱い
歴史の転換期に感染症あり
多様な血液型物質が人類を滅亡から救ってきた
第3章 ストレスに弱い体質が、A型の病気をつくる
A型の人はストレスに要注意
血液型性格診断が日本で人気が高い理由
「血液型性格学」が差別の道具にされたことも
血液型は、性格をつくる一つの要素
A型が「几帳面で慎重」といわれるのは、なぜ?
几帳面で慎重なA型の性格のルーツ
新型コロナ感染症でA型が悪化しやすいもう一つの理由
肥満の人はコロナで重症化しやすい
A型はストレス食いに走りやすい
嫌いな人と食事をしてはいけない
A型はスピード狂になりやすい
血液型の特性を知り、体とのつきあい方を理解する
第4章 血液型によってかかりやすい病気は違う
なぜ、同じ血液型にしか輸血できないのか?
A型とB型の夫婦から、 O型の子が産まれることも
血液型はどのように決まるのか
血液型の遺伝子が位置するところ
血液型のルーツをたどって自分の体質を知る
O型は躁うつ病に注意を
ピロリ菌は血液型物質が大好き
日本のノロウイルスはA型がお好き
乳酸菌にも好みの血液型がある
血液型を健康管理に生かそう
O型は風邪を引きにくい
がんになりにくい血液型ナンバーワンもO型
O型にはアスリートや総理大臣が多い
A型は風邪を引きやすい
A型はがんにも気をつけよう
ストレスにさえ気をつければA型はどんな職業でもOK
B型は肺炎や結核などに注意を
感染症に弱いがゆえに遊牧という生活スタイルを選んだ
B型はストイックに打ち込んでいるときほど病気になりにくい
AB型は病気にもっとも弱い
O型は「リンパ球人間」、AB型は「顆粒球人間」
第5章 血液型別! 体にあう食べ物、あわない食べ物
B型の人は、豚肉を毎日食べないほうがいい
体にあわない食べ物をとると、免疫力が下がる
体にあわないレクチンをとると炎症が悪化することも
O型の免疫力アップには、ダイコンおろしが吉
O型には牛肉、豚肉、羊肉があわない
O型はパンやラーメンを食べすぎてはいけない
A型の体には豚肉、ウナギがあってい
B型には羊肉やクジラ肉があい、トマトはあわない る
AB型には牛肉やブドウがよく、蕎麦には注意を
コラム ニンニクをとって免疫力アップ! コロナ禍を乗り切ろう
マスク生活だからこそニンニクを!
免疫力アップの王者はニンニク
免疫力アップの「ニンニクみそスープ」
毎日1~2片のニンニクで体調管理を
第6章 血液型別! 免疫力を上げる生活術
O型のデスクワーカーは太りやすい
O型は自然を感じながらジョギングをするといい
コロナ禍ではO型のおおらかさが周囲を明るく照らす
A型は規則正しい生活で免疫力をアップ
A型だからこそ、悠々自適な思考をもって
A型にはウォーキングや軽いジョギングがベスト
常識にとらわれない性格がB型の強み
B型は気持ちのおもむくまま好きなことをするといい
AB型にはリモートワークが最適
AB型のいるところにはAB型が集まる
AB型はのんびり散歩が性にあっている
おわりに




![オーボンクリマ イザベル ピノ ノワール 2020 【大きくなった娘と一緒に飲みたい!】Au Bon Climat Isabelle Pinot Noir [赤ワイン 辛口 フルボディ アメリカ カリフォルニア 750ml 瓶] オーボンクリマ イザベル ピノ ノワール 2020 【大きくなった娘と一緒に飲みたい!】Au Bon Climat Isabelle Pinot Noir [赤ワイン 辛口 フルボディ アメリカ カリフォルニア 750ml 瓶]](https://m.media-amazon.com/images/I/31Z8+QfxHxL._SL500_.jpg)



![【オーストラリアの ロマネコンティ と評されるピンパネル】ピンパネル ヴィンヤーズ ピノ・ノワール ワン [ 赤ワイン ミディアムボディ オーストラリア 750ml ] 【オーストラリアの ロマネコンティ と評されるピンパネル】ピンパネル ヴィンヤーズ ピノ・ノワール ワン [ 赤ワイン ミディアムボディ オーストラリア 750ml ]](https://m.media-amazon.com/images/I/31qL5qRLHJL._SL500_.jpg)

![リッポン ヴィンヤード アンド ワイナリー リッポン マチュア ヴァイン ピノ ノワール [2013] ≪ 赤ワイン ニュージーランドワイン ≫ リッポン ヴィンヤード アンド ワイナリー リッポン マチュア ヴァイン ピノ ノワール [2013] ≪ 赤ワイン ニュージーランドワイン ≫](https://m.media-amazon.com/images/I/319wzb9F7kL._SL500_.jpg)
![[2018]アタ・ランギ ”マクローン・ヴィンヤード” ピノノワール マーティンボロ[冷蔵便] [2018]アタ・ランギ ”マクローン・ヴィンヤード” ピノノワール マーティンボロ[冷蔵便]](https://m.media-amazon.com/images/I/31gUd1vABQL._SL500_.jpg)
![アタ ランギ クリムゾン ピノノワール 2022【ニュージーランドのロマネ・コンティ!】 Ata Rangi Crimson Pinot Noir [赤ワイン辛口 ミディアムボディ ニュージーランド マーティンボロー 750ml 瓶] アタ ランギ クリムゾン ピノノワール 2022【ニュージーランドのロマネ・コンティ!】 Ata Rangi Crimson Pinot Noir [赤ワイン辛口 ミディアムボディ ニュージーランド マーティンボロー 750ml 瓶]](https://m.media-amazon.com/images/I/21lYHhYswGL._SL500_.jpg)

![ポデーレ・モナステロ ”ラ・ピネタ” ピノネロ トスカーナ[ピノノワール] [冷蔵便] ポデーレ・モナステロ ”ラ・ピネタ” ピノネロ トスカーナ[ピノノワール] [冷蔵便]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Bn53A7jfL._SL500_.jpg)

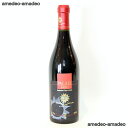
![エゴン ミュラー シャルツホーフベルガー リースリング アウスレーゼ[2021]【750ml 】EGON MULLER SCHARZHOFBERGER RIESLING AUSLESE エゴン ミュラー シャルツホーフベルガー リースリング アウスレーゼ[2021]【750ml 】EGON MULLER SCHARZHOFBERGER RIESLING AUSLESE](https://m.media-amazon.com/images/I/318TTz7LHOL._SL500_.jpg)
